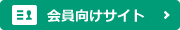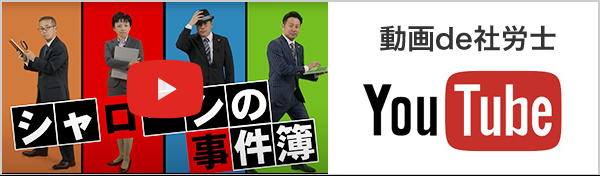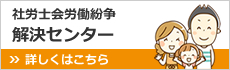個別会員情報
田中 宏明タナカ ヒロアキ
- 性別
- 男性
- 年齢
- 44歳

HRプロフェッショナル社会保険労務士オフィス
〒810-0014 福岡市中央区平尾2-5-16オネスティ平尾907
- TEL
- 092-406-3431
- FAX
- 406-3432
- info@hr-professional-sr.com
- HP
- https://www.hr-professional-sr.com/
対応可能項目
- 労働保険・社会保険の手続きの依頼
- 就業規則等の社内規定の整備の依頼
- 年金についての相談
- 給与計算の依頼
- 教育研修セミナー講師・原稿執筆の依頼
- 助成金についての相談
- 人事制度や労務管理についての相談
- 労使関係や労働紛争についての相談
- 安全衛生についての相談
- その他の相談(各種コンサルティングなど)
対応可能業種
- 建築業
- 販売業
- 製造業
- 旅館・飲食業
- 医療・福祉業
- サービス業
- 運送業
- 金融・保険業
- IT関連業
- その他
対応可能事業規模
- 1,000人以上
- 300~999人
- 100~299人
- 30~99人
- 30人未満
- 共同組合等の団体
- 個人
カバーエリア
- 福岡市
- 北九州市
- 朝倉市
- 飯塚市
- うきは市
- 大川市
- 大野城市
- 大牟田市
- 小郡市
- 春日市
- 嘉麻市
- 久留米市
- 古賀市
- 田川市
- 太宰府市
- 筑後市
- 筑紫野市
- 中間市
- 直方市
- 福津市
- 豊前市
- 宮若市
- 宗像市
- 柳川市
- 八女市
- 行橋市
- みやま市
- 糸島市
- 田川郡
- 遠賀郡
- 糟屋郡
- 三潴郡
- 京都郡
- 鞍手郡
- 八女郡
- 嘉穂郡
- 朝倉郡
- 築上郡
- 三井郡
- 那珂川市
主な経歴
【HRプロフェッショナル社会保険労務士オフィス】
代表 社会保険労務士 田中 宏明
慶應義塾大学商学部商学科 卒業
慶應義塾社会保険労務士三田会 所属
多業種での企業人事の実経験(人事・労務・採用・研修)を有しています。
「いわゆる画を描くだけではなく」、「理論や空論で決して終わらない」を信念に、
いわゆる「ジョブ型人事制度」やそれにマッチした「評価制度」の策定から導入、運用まで
スタッフ一同、力強くご支援しています。
専門分野
【ジョブ型人事制度と評価制度の策定、導入】
人事制度はシンプルに考えるべきです。「職務(ジョブ)の範囲を明確にする」、具体的には職務の範囲や責任の所在、その職務に必要なスキルと想定賃金を会社と従業員で何度も何度も話し合って決めていき、それらをジョブディスクリプション(職務記述書)としてまとめていくことが必要です。
そして評価制度ですが、敢えて申しますと「客観性のある(と信じている)評価を実施し、賃金(処遇)に反映させる」ということは「永遠に叶わないテーマ」です。私は企業人事としての経験も踏まえて、これが現実と考えます。どうして上司とはいえ「一人間」が、部下である「一人間」を客観的に、公平感をもって評価できるのでしょうか?
冷静に考えれば、無理だということは誰でも分かることです。しかしながらこれらが実現できるということを主張される方々が多いのも実情です。それについての意見はここではお伝えいたしませんが、もしジョブ型人事制度の定着・深化を強く実現されたいと思われるのであれば、現実には「割り切った」評価制度が必要となると考えます。
〔具体的な提供内容〕
・ジョブ型人事制度の策定・導入
・人事制度に適合した評価制度の策定・導入
【労務コンプライアンス研修】
「事業は人なり」。経営の神様と謳われている松下幸之助さんの言葉です。数多くの中小企業にとって新規事業を展開するにしても、人材不足で苦慮しているのが現実です。まさに人材こそ「経営の本質的な資源」であることは紛れもありません。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆるパートタイム・有期労働法等)に係る最高裁判決、労働時間に関する協定(36協定)の厳格化など、経営幹部は当然として、すべての働く人が時代の要請である「働き方改革」、「同一労働同一賃金」などの基礎を理解しておくことこそ、時代の要請である労務コンプライアンスへの対応と、延いては企業としての差別化にも繋がるのです。
〔具体的な提供内容〕
■「同一労働同一賃金」最高裁判決から「働き方改革」の本質を学ぶ労務研修
■「ハラスメント(セクハラ・パワハラ)」に関するコンプライアンス研修
■ビジネスマナー・ロジカルシンキング等を学ぶ「新入社員教育研修」
■経営トップ以下、全従業員で考える「自社の経営ビジョンと経営方針」深化研修
【助成金申請】
私たち社会保険労務士が専門とするのは「厚生労働省管轄の雇用関係の助成金」です。
人を雇い入れたり、不測の事態の際でも従業員の雇用を守ったり、人材教育その他就業環境を整備した際など、企業の雇用に関する取り組みに対して国から支給されるもので、原則として返還の必要がありません。
ただしその支給には、申請に際して多くのステップを踏む必要があり、労働法上においても、助成金の専門家である社会保険労務士への依頼が必要不可欠です。
私たちには多くの助成金の申請・獲得実績があり、たとえば、助成金の申請の中でも特に申請資料等が多く労力が必要な部類の1つである「人材開発支援助成金(特定訓練コース)」(いわゆる正社員の研修費用に関する助成金)において、豊富な実績を有しています。
〔具体的な提供内容〕
■各種助成金(「人材開発支援助成金(特定訓練コース他)」、「キャリアアップ助成金」等)の申請
主な実績
■「ジョブ型人事制度」の策定・導入から定着支援までの人事労務コンサルティング
■正社員研修等に係る助成金(「人材開発支援助成金 特定訓練コース」)獲得実績
■社員教育研修(登壇講師含む)
アピール
長年、企業人事に携わらせて頂くなかで「人事制度」や「評価制度」で悩んでいる企業様が多いと感じています。私自身、企業に人事として勤務していた頃は、いわゆる年功序列とほぼ同じである「職能資格制度」が主流であり、企業側としては「能力を適切に評価して処遇に反映してる」という主張である一方、従業員側からは「等級や号棒のアップ・ダウンの根拠が分からない。結局は年功序列ではないのか?」、「結局は評価者の好き・嫌いで昇進や昇給が決まっているのではないか?」という疑問の声がよく上がり、人事評価制度が時の経過とともに形骸化していくのを目にしてきました。多くの企業様で、今でもこれに近しい現象が起きているのではないでしょうか?人事評価制度の導入が単に「イベント化」し、「支援者」を名乗る(自称・人事コンサルを名乗る)人たちに振り回され、その後制度が「形骸化」していくのは非常にもったいないことです。
最近では、労働力人口の減少や企業のグローバル化、国を挙げての多様な働き方を推進する流れが顕著になり、「ジョブ型人事制度」が注目を集めるようになりました。同一労働・同一賃金の社会的な流れ、職務に応じて給与を支払うということの正当性について、少しずつ社会に浸透しつつある雰囲気もありますが、ジョブ型人事制度と言っても、「ジョブディスクリプション(職務に関する記述書)はどこまで網羅すれば良いのか?」、「賃金はどのように決めるべきか?」、「評価と賃金等の処遇はどのように関係づけていくべきか?今の評価制度とどう違うのか?」など、ジョブ型人事制度の導入に際しては相当「タフな問題」が山積しており、導入の道半ばで断念される企業様も多いように見ています。
私たちには企業での人事労務の豊富な「実経験」があり、かつ最新の労働法に関する「専門知識」を駆使して、企業人事の皆様のこのようなお悩みに寄り添い、制度の策定・導入から運用まで、これまで徹底して伴走してきました。
今後ともHR(人事)関連業務のプロフェッショナルとして、皆様の「役割期待(ジョブ)」を完遂して参ります。